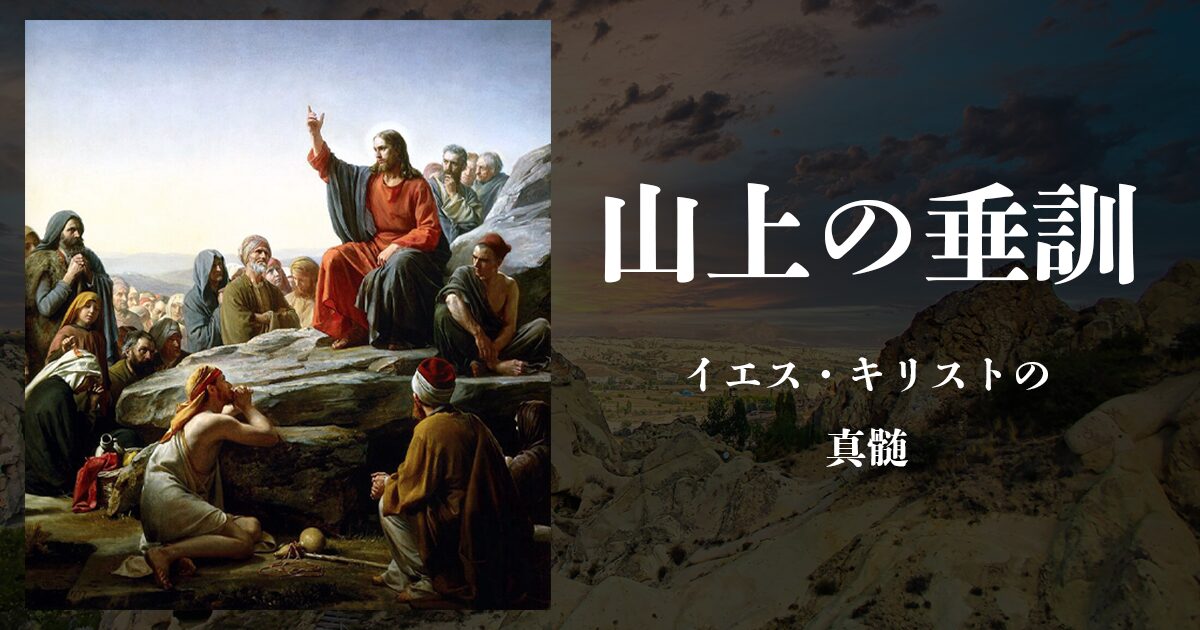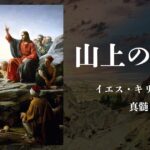聖書を読む上で、特に福音書を読む上で、もっとも重要な箇所の一つであるのが、山上の垂訓である。僕は、この記事を書くにあたって、単なる一信仰者である自らが、註解紛いの事をする事により、世間から受ける目線を思うと、この記事を発表する事に少し迷った。しかし、キリスト信仰の真髄を示す役目は、我々一人一人のキリスト者に与えられているのだと信じて、この記事を捧げる事にした。
山上の垂訓とは、キリストの述べた最も体系的な教えで、マタイによる福音書第5章から第7章によって記されている。イエスは「山に登り、座につかれ」て、その言葉を語り始めた。
これを読む事で、キリスト者が何に従う者であるのか、何に従うべき者であるのかが分かる。キリスト信仰の真髄はまさにここにある。多くの人が、この文章を読む事で、ここに述べられた真理を糧にして生きられるよう祈る。
祈り
キリスト的なものは間違いなく、世界に実現されていると信じること。彼に従わない者への言葉を吐ける程、自ら立派でないということを知ること。そして、キリスト者であるならば、この世は善で満ちていて、このあらゆる恩寵に感謝し、その上で、常に絶えず喜び、絶えず喜捨すること。
キリストの真髄は常に毎日発見される。生ける泉がキリスト信仰の中にある。彼の言葉は間違いなく、この世の真理を示しており、この上なく、預言者以上のものであり、我が主、我が神であるとはっきり言おう。僕の喜びは、全て神の恩寵から来ている。それへの感謝以外に、何らするべき事はなく、苦しい時も感謝し続けること。
彼の言葉は生き続ける。彼の言葉は決して滅びる事がない。もはや、彼への信仰表明、それのみに意味がある。
だから、完全な者になれますように。あなたの、山上の垂訓、その真髄を全て果たせますように。
本文解説
まず、イエスは、どのような人が「幸い」であるかを8回にわたって述べる。そこには、普通は幸せとは思えない状態が含まれる。しかし、一見満たされていない状態である人間も、既に神によって満たされていることなど、深い意味が隠されているのである。
[3] 「心の貧しい人々は、幸いである、 天の国はその人たちのものである。
マタイによる福音書 5:3 新共同訳
心の貧しい者とは、多くを求めない者である。多く、とは、自らの為の欲望として多くを取らないもの。[同様に、心の器が空っぽで、そこに霊的なものが注ぎ込まれるものを指している。]そのようなものにとって、与えられるものは僅かでも極めて貴重で、地上すらも天の国となる。
[4] 悲しむ人々は、幸いである、 その人たちは慰められる。
マタイによる福音書 5:4 新共同訳
悲しむ程に心が清く、素直に感情を持つものは、神による慰めを受ける。そのような者に、人々や、世界、運命は、居てもたってもいられない。むしろ、悲しむことが出来るということが、慰めですらある。それは、恩寵を待ち望んでいるからだ。
[5] 柔和な人々は、幸いである、 その人たちは地を受け継ぐ。
マタイによる福音書 5:5 新共同訳
柔和な人は、人々からの信頼を寄せられ、この地において多くを得る。柔和である事によって多くを得て、また、柔和で有り続ける事によって得るものを、正当に感謝して使う事が出来るものだ。
[6] 義に飢え渇く人々は、幸いである、 その人たちは満たされる。
マタイによる福音書 5:6 新共同訳
義に乾く人達は、正義を実現しようと世界で闘う中で、やがて義が実現していき、彼らの思いは満たされるものだ。
[7] 憐れみ深い人々は、幸いである、 その人たちは憐れみを受ける。
マタイによる福音書 5:7 新共同訳
人に憐れみを施すものは、同じく人に憐れまれるようになる。
[8] 心の清い人々は、幸いである、 その人たちは神を見る。
マタイによる福音書 5:8 新共同訳
心の清い、とは、真っ直ぐ、真面目に生きている人々である。そのような人は、確かにこの世に、被造物の中に顕現した神を見るものだ。僕も、また、キリスト者へ改心した知り合いも、共通点は真っ直ぐさであった。真っ直ぐに生きるとは、理(ことわり)に忠実であるということで、それを続けると、理そのものである神を見る事になる。
[9] 平和を実現する人々は、幸いである、 その人たちは神の子と呼ばれる
マタイによる福音書 5:9 新共同訳
この世に平和を実現する人は、人々に神の子と呼ばれるに相応しいということだ。ハレルヤ!我が主イエス・キリストはまことに神の子、神の独り子である。彼に聖化されて、自らも神の子と呼ばれるに相応しい者になれますように。
[10] 義のために迫害される人々は、幸いである、 天の国はその人たちのものである。
マタイによる福音書 5:10 新共同訳
ここまで、「天の国」は、超越的世界としても解釈できるが、内面世界のものとしても十全に解釈出来ることを示したつもりである。今回もその例に漏れない。義の為に迫害されるものは、その信仰と、その帰依によって、天の国を与えられる。彼らの内面世界こそが天の国である。
[11] わたしのためにののしられ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪口を浴びせられるとき、あなたがたは幸いである。 [12] 喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなたがたより前の預言者たちも、同じように迫害されたのである。
マタイによる福音書 5:11-12 新共同訳
正しき者への帰依。それによって罵られる時、それは喜ばしい事である。それは、かつての偉大な者たちの道筋と、同じ道を辿っている事の証左である。
[13] 「あなたがたは地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味が付けられよう。もはや、何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。 [14] あなたがたは世の光である。山の上にある町は、隠れることができない。 [15] また、ともし火をともして升の下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば、家の中のものすべてを照らすのである。 [16] そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。人々が、あなたがたの立派な行いを見て、あなたがたの天の父をあがめるようになるためである。」
マタイによる福音書 5:13-16 新共同訳
「あなた方人間は、この地を満たす為に神に遣わされ、内々に大いなる光をともし、その崇高なものの為に存在している。だから、その光を人々に輝かせなさい。決して、光を消さないように。」という事だと解釈した。まさに、キリスト信仰とはこのようなものである。愛の為に律法があるとは、このようなことである。
[17] 「わたしが来たのは律法や預言者を廃止するためだ、と思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。 [18] はっきり言っておく。すべてのことが実現し、天地が消えうせるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない。 [19] だから、これらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教える者は、天の国で最も小さい者と呼ばれる。しかし、それを守り、そうするように教える者は、天の国で大いなる者と呼ばれる。 [20] 言っておくが、あなたがたの義が律法学者やファリサイ派の人々の義にまさっていなければ、あなたがたは決して天の国に入ることができない。
マタイによる福音書 5:17-20 新共同訳
律法や預言者は、全て神への帰依について説いた。しかし、神への帰依とは、本質的に、条文化された行為のみによって表されるものではなく、全ての行いを通して表されるべきものだ。律法のみを守って、人の為を思わないなどという態度ではなく、真に律法的である態度─即ち、神の理に従うこと─こそが、イエスの目指すものである。
[21] 「あなたがたも聞いているとおり、昔の人は『殺すな。人を殺した者は裁きを受ける』と命じられている。 [22] しかし、わたしは言っておく。兄弟に腹を立てる者はだれでも裁きを受ける。兄弟に『ばか』と言う者は、最高法院に引き渡され、『愚か者』と言う者は、火の地獄に投げ込まれる。 [23] だから、あなたが祭壇に供え物を献げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、 [24] その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰って来て、供え物を献げなさい。
マタイによる福音書 5:21-24 新共同訳
「兄弟に『ばか』と言う」とは、悪意を持って人を罵ることだと解釈した。そのようなこと一つで、火の地獄に投げ込まれるとは、なんと厳しい罰であろう。しかし、まさにその一つ一つの行為が、神の前では問われているのだということである。捧げ物の前に、自らの心を責める咎を許して貰う方が先だ、とイエスは示す。
[27] 「あなたがたも聞いているとおり、『姦淫するな』と命じられている。 [28] しかし、わたしは言っておく。みだらな思いで他人の妻を見る者はだれでも、既に心の中でその女を犯したのである。 [29] もし、右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に投げ込まれない方がましである。 [30] もし、右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に落ちない方がましである。」
マタイによる福音書 5:27-30 新共同訳
ここの解釈は、以前からずっと僕にとって問題であった。ここでのイエスの要求は、文字通りに解釈すると、大抵の人が果たせるようなものではなくなるからだ。しかし、ようやくここで言われている事を把握した。
そもそも、十戒における姦淫とは、当時のユダヤでは不倫の事を指していた。では、不倫の何が問題かといえば、それは快楽に耽り、自己と他者を動物化して、精神的なものを殺し、関係性を破壊する事である。この説明において、しかし、心の中で人の妻をみだらに見る事は、それと全く同じである事が分かる。即ち、イエスは愛に基づく性の否定をしたのではない。むしろ、「快楽における愛の否定」を、イエスは否定したのだ。心の中で、他人の妻をみだらに見るのは、その人間同士の信頼関係を傷付けることだ。これは、訳語の問題で、「他人の妻」を「女性」としても同じことだ。つまり、ここにおいて問題視されているのは、性欲それそのものではなく、性欲による関係性の破壊、また、破壊とまではいかなくとも汚す行為である。愛より快を優先する事が問題視されているのである。
[33] 「また、あなたがたも聞いているとおり、昔の人は、『偽りの誓いを立てるな。主に対して誓ったことは、必ず果たせ』と命じられている。 [34] しかし、わたしは言っておく。一切誓いを立ててはならない。天にかけて誓ってはならない。そこは神の玉座である。 [35] 地にかけて誓ってはならない。そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない。そこは大王の都である。 [36] また、あなたの頭にかけて誓ってはならない。髪の毛一本すら、あなたは白くも黒くもできないからである。 [37] あなたがたは、『然り、然り』『否、否』と言いなさい。それ以上のことは、悪い者から出るのである。」
マタイによる福音書 5:33-37 新共同訳
あなたが誓った事を果たしたとしても、それはあなたが果たしたのではない。実に、神が果たさせるか、果たさせないかを決められるのだ。天も地も神が統べる。よって、ただ目の前のものごとそれ自体を見て、「そうであることは、そう」「違うことは、違う」と言え、ということだと解釈した。
マタイによる福音書 5:38-42 新共同訳
[38] 「あなたがたも聞いているとおり、『目には目を、歯には歯を』と命じられている。 [39] しかし、わたしは言っておく。悪人に手向かってはならない。だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい。 [40] あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい。 [41] だれかが、一ミリオン行くように強いるなら、一緒に二ミリオン行きなさい。 [42] 求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に、背を向けてはならない。」
神のようになるには、悪人に自らが侵害されても、受け入れて与えなさい、ということである。ところで、悪人が傷付ける対象が、それ以上である場合は別であると僕は解釈した。義に従うものは幸いだとあるからである。
[43] 「あなたがたも聞いているとおり、『隣人を愛し、敵を憎め』と命じられている。 [44] しかし、わたしは言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。 [45] あなたがたの天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。 [46] 自分を愛してくれる人を愛したところで、あなたがたにどんな報いがあろうか。徴税人でも、同じことをしているではないか。 [47] 自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ、同じことをしているではないか。 [48] だから、あなたがたの天の父が完全であられるように、あなたがたも完全な者となりなさい。」
マタイによる福音書 5:43-48 新共同訳
天の父のように、またイエス・キリストのように、完全な者となるためには、敵を愛せる程に自らを捨てなさい、ということだ。
終わりに
思ったより文章が長くなってしまった為、マタイ6-7章の解説はこの記事では割愛する事にした。
ここまでの文章で、山上の垂訓の真髄を理解して頂けたと思う。これらの教えに共通する根幹的なものは以下である。愛である神の理に、絶えず帰依すること。それによって、内的な光は輝く。キリスト信仰とは、本質的にはここまでシンプルなものなのである。そして、そのシンプルさが、どこまでも奥深く、求めていく価値のあるものでもあるということだ。
最後に、同じく山上の垂訓から、以下の二つを引用してこの記事を終わりにする。
[13] 「狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。 [14] しかし、命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見いだす者は少ない。」
マタイによる福音書 7:13-14 新共同訳
[7] 「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。 [8] だれでも、求める者は受け、探す者は見つけ、門をたたく者には開かれる。
マタイによる福音書 7:7-8 新共同訳
投稿者プロフィール

- 地方大学2年生。心理系学部。キリスト教、哲学、神秘主義に詳しい。プラトン、アウグスティヌス、内村鑑三、キルケゴール等が愛読書。
SNS
X(旧twitter)
最新の投稿