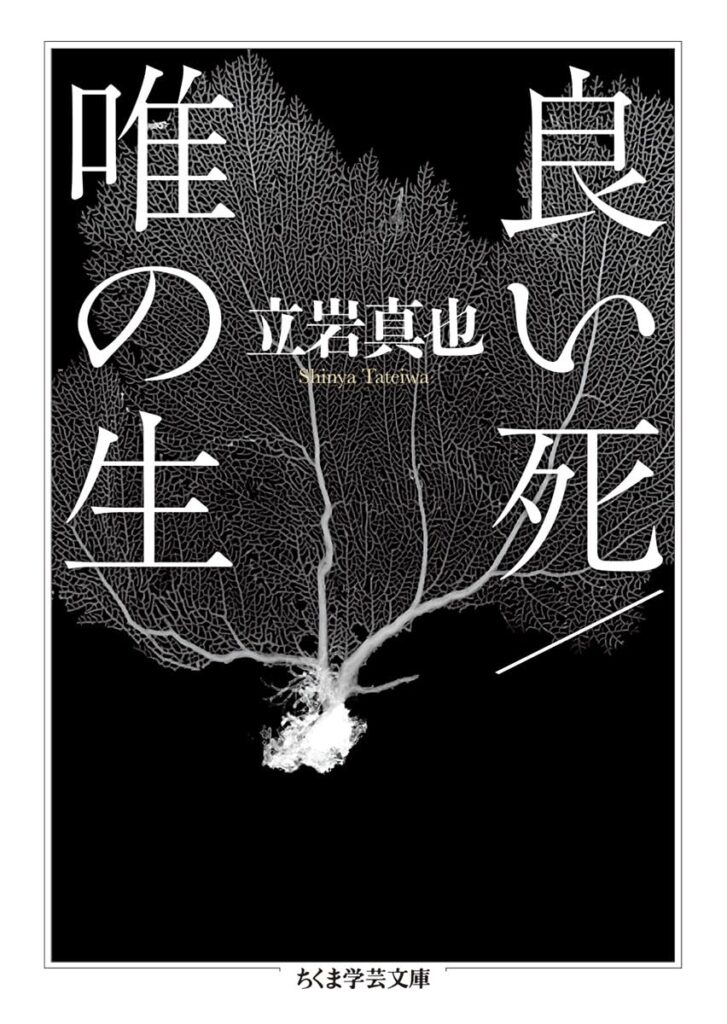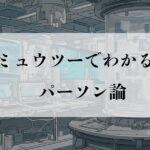立岩真也は2023年に亡くなった日本の社会学者で安楽死や障がい関係の研究者で知らないものはいないだろうという人物だ。
しかし僕は恥ずかしながら、学部時代、その存在を知らなかったし、著作を読んだこともなかった。初めてその著作に触れたのは2015年のことだった。指導教授から、生命倫理学をやるなら読め、発表してみろと勧められたのが最初だ。
独特の文体で読み込むのは大変だったが、その知識と洞察に圧倒され、仏教者の先輩が「現場を知らない!」と憤慨したという中、僕は世界に希望を持つことができた。どんなときも今を楽しむ重要さを学んだのだ。その後修士論文としては脳死の問題だったので立岩節を使用することはなかったが、現在までに通算3回『良い死』を題材に発表している。
残念ながらコロナ禍ゆえに対面でお会いすることはできなかったが、立岩研究を今後も続けていきたいと思っている。さて、ここまでのストーリーで『良い死』に興味を持った方のために、少しだけ内容にも触れておこう。
今『良い死』は文庫本になっている。その『良い死/唯の生』(文庫版)の帯には、こんなことばがあった。
「唯の生」で良い
誰でも「生きたいなら生きられる」社会へ!
立岩真也『良い死』 帯文
「唯の生」とはなんだろうか。「ベッドで横になっている〝だけ〟の生」のことだろうか。そして、「誰でも「生きたいなら生きられる」社会へ!」と煽るということは、今はそういう社会ではないということだろうか。この本は、そういったことを考えさせられる内容となっている。
では『良い死』はどんなこと議論するのか「文庫版への序」には次の文章が躍っている。
「良い死」を追い求めるのはよそう、「唯の生」でいい
立岩真也『良い死』p11
「序」には次のようにある。
『良い死』では、自分で決める、自然な(そして/あるいは美しい)、そして利他的な死として肯定される死ついて考える。同時に、たしかにあまりぱっとしない生を否定しないほうがよいと述べる。
立岩真也『良い死』p17
ずっと起こってきたことは、自己決定がどうしたというようなことではなく、「終末期」に関わる様々をきりつめようという以外のことではなかった。
立岩真也『良い死』p18 強調は引用者
さらに「序章 要約・前置き」では、重要なことが説明されている。それは、「延命措置」は悪い意味で使われるようになったが、本来は空腹や呼吸困難などの「苦しさ」を和らげているという事実だ。ときに我々は延命措置について悪い面ばかりを見過ぎていたことを本書は語り掛けてくる。
今日では人生会議をはじめ、「どう死ぬか」を決める自由がある。同時にそれは決める義務ともなっているかもしれない。本書は《健康な時には実感はないのに事前指示の通りになってしまう》という問題を我々に教えてくれる。立岩は、苦痛から尊厳死解禁を訴える前に、苦痛緩和が先決。苦痛を緩和できれば尊厳死は減らせると主張する。
例えば意識がなく「ベッドで寝ているだけの人生」は本当に悪いのだろうか。本人にはもう意識がないのだから、良くも悪くもないというのが事実ではないか。早く死にたい理由もないではないか。本書はそう主張する。
確かに本人に益のない処置はやめても良いだろう。だがそのための法改正は必要ないというのが立岩の立場である。
こうなると、延命を拒否する理由とは、《周囲に迷惑をかけたくない》が大きいのではないかと考えることになる。
「第1章 私の死」に進むと、さらなる延命拒否の強い理屈が登場する。それは、《私のことは私が決める、だから安楽死・尊厳死を解禁しろ》だ。我々はこの論理にひるみがちだが、立岩はひるまない。《他者危害原則に抵触しているのではないか?》と疑問を呈する。例えばその自己決定に社会的・経済的要因があるのではないか? 《あなたのお好きにどうぞ》の前に考えるべきことを本書は教えてくれるのである。
本書では「」付の《哲学的問題》も扱われる。それは「事前指示書」について現れる。つまり、今の健康な自分が未来の病気の自分の決定を代わりにする権利があるのかということである。
「未来の私」のことを「私のこと」として決めることは自明ではないというのが本書の主張である。そこにあるのは、現在の私と未来の私の同一性の問題である。現実的には、現在の私と未来の私の利害が一致する場合にはあまり問題はないだろう。しかし認知症になった等を想像して決定しておくことには問題があると本書はする。長いが重要だから引用しておこう。
「意識を失った……人自身には快苦もない。その人は、そうなってしまった状態を、生きている人の最善の利益によって決めていると言えない。その人はむしろ、決定の時点において、その時点での私が、将来想像されるような私になることが耐えられないのである。「事前」に決めようとしているその今の自分にとってよいことをしているのであり、その時にそうなっているその私にとって有利なことをしているのではないだろう。それはその時の私の利益ではない。私は認知症になった。……その時の私には死にたい理由はない。生きたいと思っているかもしれない」
立岩真也『良い死』 p145ーp146 改行は引用者が省略
以上、序盤で面白い部分をいくつか紹介した。長い本で癖もあるが、生命倫理の問題に興味がある方はぜひ読んでみてほしい。
※引用のページ数はすべて「良い死/唯の生 (ちくま学芸文庫)」より
投稿者プロフィール

- 生命倫理相談所運営者 京都府立医科大学研修員 生命倫理学と宗教学が専門 好きな研究者は、冲永隆子、森岡正博、小松美彦、立岩真也など
SNS :X
最新の投稿